電機システム研究室
[English]
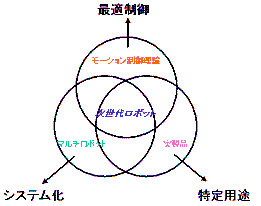 教授
平井 淳之
教授
平井 淳之
hirai@elec.mie-u.ac.jp
准教授
駒田 諭
komada@elec.mie-u.ac.jp
准教授
弓場井 一裕
yubai@elec.mie-u.ac.jp
技術員
中村 勝
nakamura@elec.mie-u.ac.jp
電機システム研究室ホームページ
昭和44年の電気工学科創設時からの「電力工学」講座が発展して, 平成 3 年に「電機システム」研究室が開設され,
現在に至っている.この間, とりわけ昭和60年代に入ると, エレクトロニクス技術の格段の進歩につれて,
大学研究室における「電力工学」分野の研究課題はエレクトロニクス技術を利用した電力変換と制御,
すなわちパワーエレクトロニクス,
モーションコントロール, さらには機械系と融合によるメカトロニクス(特にロボット)に,
その主体を移してきた.当研究室においても, この流れを経て, 更なる知的モーション制御,
近未来の人間社会において奉仕, 共生するロボットおよび, そのシステム化へと研究の対象と段階を発展させている.
ロボットは,従来から産業用として生産ラインなどで広く用いられているが,
今後は福祉・介護やアミューズメント用として,深く人間社会に入り込んで行くと考えられる.
その際,ロボットが人間と協調・共生していくためには,
位置・力・画像など外界から取り込まれる様々なセンサ情報を基に,
適切な行動を選択・実行しなければならない.
それにはロボット自体が人間が有する様な高度な判断機能を持ち合わさなければならない.
また,正確な動きもさることながら,人間との共同作業を想定した柔らかな動きも要求されるため,
どの様にして人間らしい動きを実現するかを考える必要がある.
更にロボットの社会進出が進むと集中管理が困難となるため,
故障が発生したとしても自ら検出し対応できる自律性の高いロボットの実現が望まれる.
この様に人間との協調・共生を目的とした
ロボットのモーションコントロール研究には非常に興味深くかつ未開の課題が数多く存在している.
当研究室は以上の観点に立って次世代ロボットを核とし,
なすべき研究開発を上図の様に3つに大別,方向付けして,その実現に向けて活動を行っている.
最近の当研究室における研究事例は以下である.
1. モーションコントロールの研究
ロボット駆動・制御において基本的な要求である高速かつ正確な動作を実現するための研究を行っている.
現実のロボットにはクーロン摩擦やバックラッシュなどの非線形性が数多く存在しモデル化誤差も存在することから,
高精度な制御が困難な場合がある.そこで,モデル化誤差や環境の不確かさが存在しても制御性能の劣化を生じさせない様な外乱オブザーバやH∞制御などを用いたロバスト制御に関する研究を進めている.
2. ロボットの知能化とシステム化の研究
人間の様に自律的に動作を行うことのできるロボットを実現するために, カメラから得た画像情報を基に動作戦略を考え,
動作を実行できるロボットの開発を手がけている.また人間の器用で柔軟な動作をロボットにおいても実現するために,
人間の腕の動作戦略を解析し, その結果をロボット制御へ応用することを研究している.さらに,
複数台のロボットが協力して目的を達成するシステムを実現するために, ロボット間協調動作の研究をも進めている.
3.目的を特定した次世代ロボットの研究
加えて,上述の新制御理論や革新的なアクチュエータを使い, 人間と共生できるロボット,
あるいは特化作業において人間の機能・性能を大きく越える様な次世代ロボットの研究・開発をしている.人間と共生できるロボットを実現するために,
マニピュレータのインピーダンス制御やファジィ的な意志決定手法などの理論とともに無接触モーション伝送などの新概念を取り入れ,
組み替え可能なモジュラーロボットなど, 新構成のロボットの実現を目指している.またロボットの操作対象としては,
人間の下肢や生体(細胞等)をも想定し,
巧みなモーション制御により対象物に優しいハンドリングを行う研究も始めている.
www-admin@elec.mie-u.ac.jp
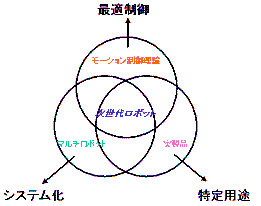 教授
平井 淳之
教授
平井 淳之